ブラックバスは外来種って聞いたことがあるけど、雷魚も外来種? 普段から接している釣り人ですら、なんとなく知っているけれど、詳しくはわからないという方も多いのではないでしょうか。 この記事を読んでいただくことで、雷魚って「外来生物なの?」「特定外来生物って何?」などといった疑問を解決できます。
ブラックバスや雷魚は外来種なの?
ブラックバスは、1925年米国から移入した外来種。 雷魚は、カムルチーとタイワンドジョウとコウタイの総称ですが、いずれも外来種。 カムルチーは、1923〜1924年頃、朝鮮半島から移入した外来種、 タイワンドジョウも、1906年に、台湾から移入した外来種、 コウタイは、1960年代に台湾から移入した外来種です。 ブラックバスも雷魚も、もともと日本にいなかった生物であるため、外来種です。 そんなこと言い出したら、元を辿れば、かなりの種が外来種なんじゃん?と思ってしまうのですが、環境省HPに下記のように記載がありました。
外来生物法では海外から日本に持ち込まれた生物(国外由来の外来種)に焦点を絞り、人間の移動や物流が盛んになり始めた明治時代以降に導入されたものを中心に対応します。
明治時代は、1868年〜1912年ですから、ブラックバスも雷魚も、上記に該当しますね。 では、外来種だったら全て害はあるの?といえばそんなことはなく、例えば、子供の頃から馴染みのある4つ葉のクローバー、あのシロツメクサも外来種です。  ちょうどブラックバスをシロツメクサの上に置いて撮影した写真がありましたが、このどちらも外来種なんですね。 釣り人の間では、「特定外来生物」に該当するかどうかが焦点になります。 ブラックバスは「特定外来生物」に指定され、バスフィッシャーマンの肩身が狭くなってしまいましたから。。。
ちょうどブラックバスをシロツメクサの上に置いて撮影した写真がありましたが、このどちらも外来種なんですね。 釣り人の間では、「特定外来生物」に該当するかどうかが焦点になります。 ブラックバスは「特定外来生物」に指定され、バスフィッシャーマンの肩身が狭くなってしまいましたから。。。
特定外来生物とは?雷魚は特定外来生物ではない?
2005年6月1日に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」が施行されました。 長いので以下、「外来生物法」と略します。 「外来生物法」とは、簡単に言うと、問題を引き起こす海外起源の「特定外来生物」なるものから、在来種の生態系、作物などを守る法律です。 一般的に、「特定外来生物」に認定されたら、「悪だ」と認識されている印象もあります。 確かに、日本の在来種の生態系を壊す恐れがあるという点では、悪です。 しかしながら、「ブラックバスやブルーギルって怖い魚なんでしょ」などといった認識を持たれている方が多いのは残念でなりません。 以前、滋賀県琵琶湖の漁港で釣りをしている時に、小学生くらいの女の子4人を見かけました。 そのうちの一人が琵琶湖の水面に近づこうとした時、他の3人が大きな声をあげて、水面に近づいた一人を必死になって止めていました。 「やめときーや、ブラックバスとかおるんやで、ブラックバスに噛みつかれたら知らんで!」と。 また、お父さんと二人で釣りに来た小学生くらいの男の子が、餌で釣り上げたブルーギルを、ポイポイと草むらに捨てている光景を目にしました。 琵琶湖は、確かにリリース禁止なので水に返してはいけないのですが、子供が、命を無惨に草むらに捨てるのはいかがなものでしょうか。 バタバタ暴れまわって苦しんでいる魚を見てなんとも思わないのか、そのお父さんはどんな教育をされているのか、と憤りを覚えました。 琵琶湖で釣り上げたブルーギルとブラックバスは、外来魚回収ボックスに入れなければならない決まりになっていますが、釣りを覚えたての子供にそれを強いるのも、文脈を理解せずに単に「あの魚は悪だ」と教えるのも、個人的に違和感を覚えます。 電気ショックなどで駆除している専門の人が居るのだから、それでいいではないか、と思うのです。 ブラックバスもブルーギルも、日本でちょっと難しい事情があるだけで、本来の生息地ではごく普通の生き物として生息して居る魚なんです。もちろん、人間に悪はありませんし、噛み付くこともありません。とっても可愛い魚です。 話を元に戻します。 「特定外来生物」には以下のような種が含まれます
 雷魚とオオモンハタを足して2で割ったようなかっこいい魚ですね。 特定外来生物は、飼育、保管および運搬、輸入、放出、譲渡、引き渡し、販売、飼育が禁止されています。 ※琵琶湖などの特定の地域では例外ですが、釣りの「キャッチアンドリリース」は規制対象ではありません。 特定外来生物リスト以外に、特定外来生物リストには漏れた「サブのリスト」があります。 それが、「生態系被害防止外来種」 「特定外来生物」の枠には漏れたけれど、要検討中ですよ〜というリストです。 危険度で表すと、「特定外来生物」>「生態系被害防止外来種」となるわけですね。
雷魚とオオモンハタを足して2で割ったようなかっこいい魚ですね。 特定外来生物は、飼育、保管および運搬、輸入、放出、譲渡、引き渡し、販売、飼育が禁止されています。 ※琵琶湖などの特定の地域では例外ですが、釣りの「キャッチアンドリリース」は規制対象ではありません。 特定外来生物リスト以外に、特定外来生物リストには漏れた「サブのリスト」があります。 それが、「生態系被害防止外来種」 「特定外来生物」の枠には漏れたけれど、要検討中ですよ〜というリストです。 危険度で表すと、「特定外来生物」>「生態系被害防止外来種」となるわけですね。
生態系被害防止外来種とは?
先述の特定外来生物の枠には含まれないが、以下のような恐れのある生物を、「生態系被害防止外来種」と言います。
1.生態系被害が大きいもの。 2.生物多様性保全上重要な地域に侵入し、問題になっている又はその可能性が高い。 3.生態系被害のほか、人体や経済・産業に大きな影響を及ぼすもの。 4.知見が十分でないものの、近縁種や同様の生態を持つ種が明らかに侵略的であるとの情報があるもの、又は、 近年の国内への侵入や分布の拡大が注目されている等の理由により、知見の集積が必要とされているもの
出典: 出典: 環境省のHP
これでは、ちょっと特定外来生物との違いが分かりづらいですね。 生態系被害防止外来種に含まれ、かつ特定外来生物にも含まれる生物が居て、 特定外来生物に含まれ、かつ生態系被害防止外来種に含まれる生物が居ないことからも やはり、「特定外来生物」>「生態系被害防止外来種」という図式で考えるのが分かりやすいです。 さらにいうと、生態系被害防止外来種にも含まれない外来種もたくさんいるので、 「特定外来生物」>「生態系被害防止外来種」>「被害の恐れのない外来種」という図式になります。 また、特定外来生物は、外来生物法という法律によって定められているが、生態系被害防止外来種は、法律では定められていないけれど侵略性が確認されているものと認識すると分かりやすいかもしれません。 生態系被害防止外来種には、記事作成時で全429種類が登録されています。 全429種類もあるので、全ては挙げませんが、よく知られた魚類では、ソウギョ、グッピー、ティラピア、タイリクバラタナゴ、ニジマス、ブラウントラウト、レイクトラウトなどがあります。 グッピーやタイリクバラタナゴが、ティラピアと並列で並ぶのにはすごく違和感がありますね。 僕は、タイリクバラタナゴを、幼い頃、近所の川で採ってきて飼育していたことがありますが、数年後には近所の川で姿を見かけなくなり、絶滅危惧種として認識していました。 違うんですね、絶滅危惧種はニッポンバラタナゴであり、タイリクバラタナゴは外来種でした。 ニッポンバラタナゴとタイリクバラタナゴの交雑種と判断された事例もあるようです。 あんなに綺麗な魚が、生態系被害防止外来種とは、なんだかちょっと切ない気分です。 また、生態系被害防止外来種に、ハス、モツゴ、ギギなども含まれます。 これらは外来種ではありません。 「国内由来の外来種」とされています。
分かりやすい例を挙げると、カブトムシは元々北海道にいませんでした。 よって、北海道のカブトムシは、国内由来の外来種であり、生態系被害防止外来種なんです。 つまり、ハス、モツゴ、ギギも、地域によっては、生態系被害防止外来種なんですね。 ハスは、琵琶湖・淀川以外のハス。 モツゴは、東北地方などのモツゴ。 ギギは、九州北西部および東海、北陸地方以東のギギに限って、国内由来の外来種であり、生態系被害防止外来種です。 本題に戻ります。 そうです、雷魚の名前が無いのです! カムルチーともタイワンドジョウとコウタイとも表記がありません。 タイリクバラタナゴやグッピーがリストに入っていて、小型の魚類やカエル類を捕食する、あのどう猛な雷魚が無いのです! しかも、北海道,本州,四国,九州のほぼ全域で生息が確認されています。 以前は、「要注意外来生物リスト」に登録されていた、との文献を見つけました。 しかし、「要注意外来生物リスト」とは、生態系被害防止外来種リストの作成に伴い、平成27年3月に廃止されたそうです。 つまり、要注意外来生物リスト ≒ 生態系被害防止外来種リストということでしょうか。 でも、現在では、生態系被害防止外来種リストに雷魚はありません。 よって、現状、特定外来生物でも生態系被害防止外来種でもない雷魚は、ただの外来種。 つまり、雷魚は、被害の恐れのない外来種ということになります。 釣り人としては、嬉しいこととも言えますが、釣り人であり普段より様々な魚を目にしている僕にとって、ニジマスやブラウンよりも侵略性がないとは考えにくいのです。 なぜ、雷魚は、特定外来生物からも生態系被害防止外来種リストからも外されたのでしょうか。 その経緯について詳しくは分かりませんが、実際に、生態系に被害を及ぼした明確な被害状況が確認できていないから、要観察とされているそうです。 全国の水域で減少傾向にある雷魚です。 一見ギョッとするような見た目をしていますが、よく観察すると可愛い顔をした魚です。 日本の生態系に被害の恐れのない外来種であるなら、なおさら、大切に接していきたいですね。
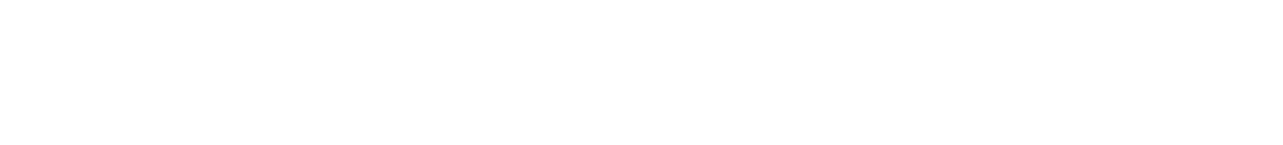
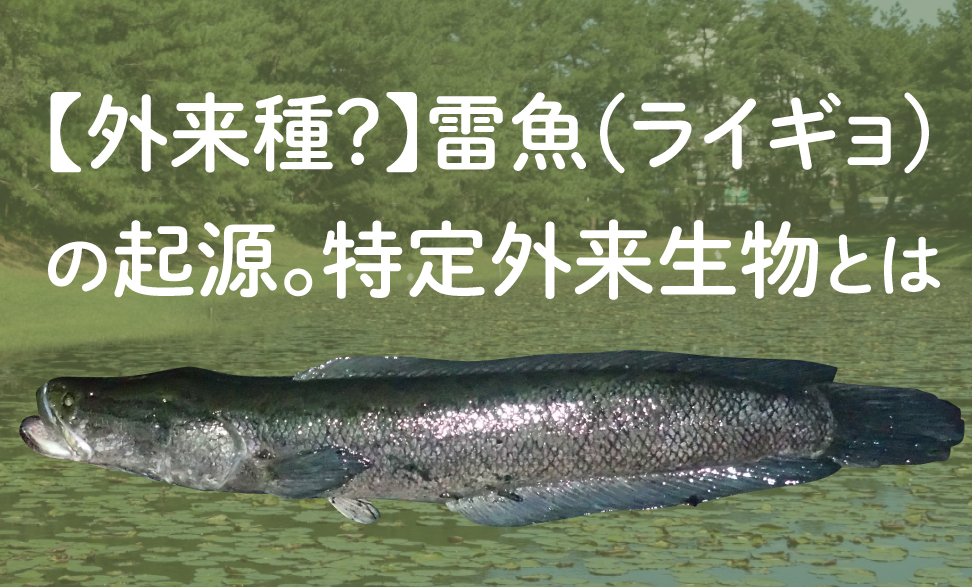

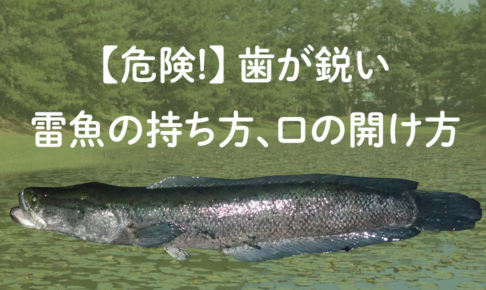






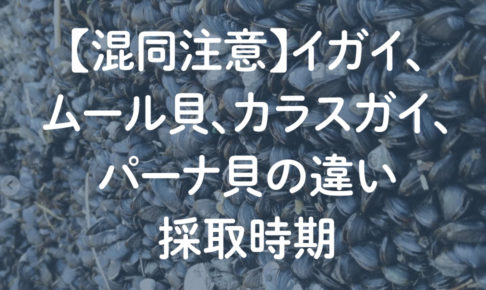
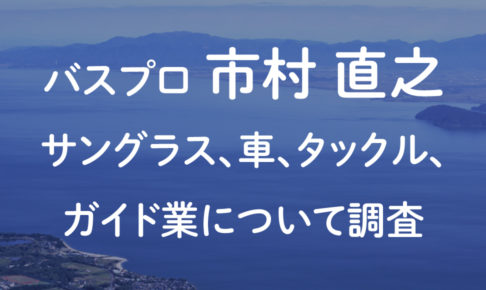
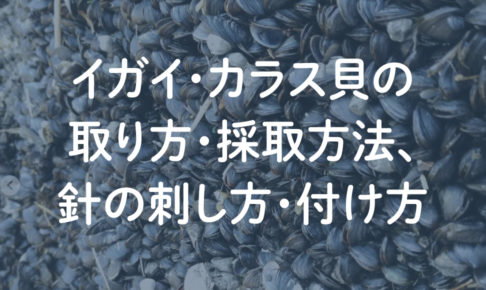
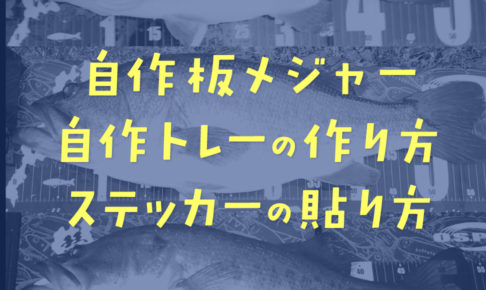
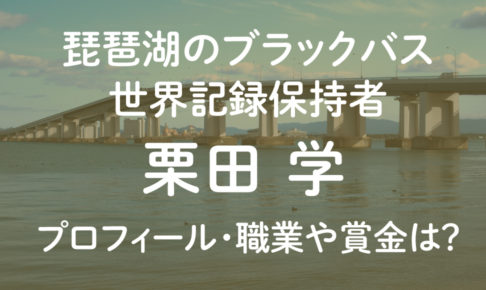
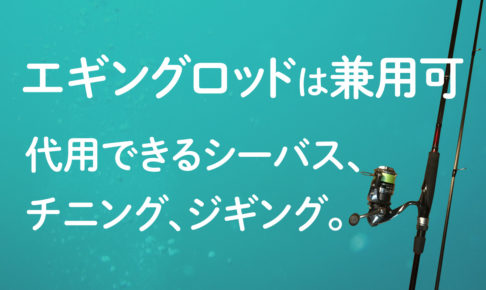
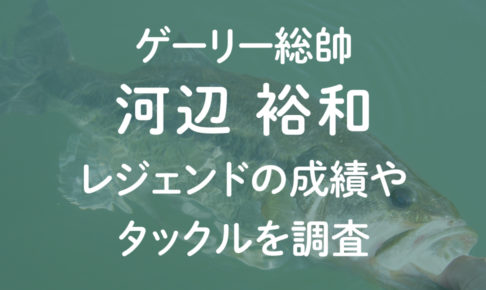
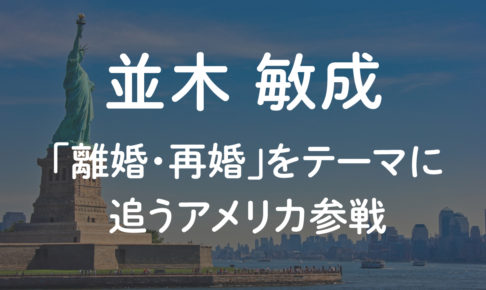
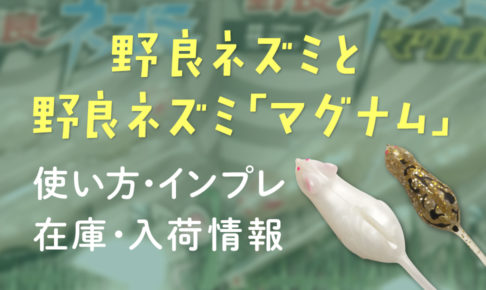
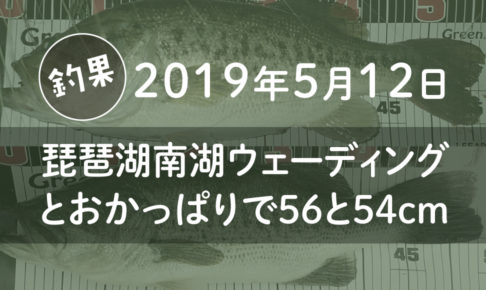
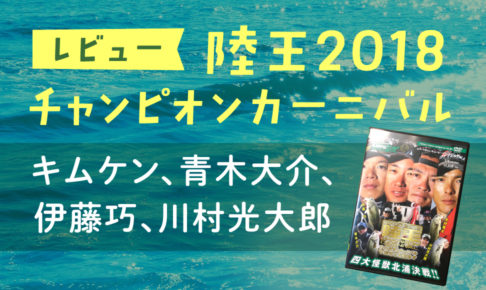
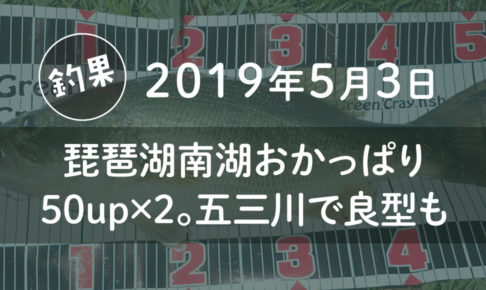
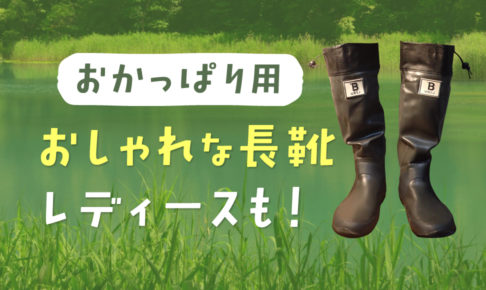
コメントを残す